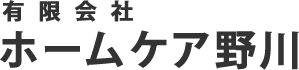主任ケアマネ研修3.4日目(SV)
2025/01/17
おはようございます!
冬晴れの日が続き、年を開けてから寒さが増しました。
雨もあまり降らないので乾燥からかインフルエンザが流行っています。
みなさま体調管理、気を付けましょう。
毎年感じていて利用者の方にも話すのですが、この時期精神的にも身体的にも体調を崩される方が多いです。
「急に転倒するようになった。」とか「急に今までにない変なことを言い出すようになった。」とかです。
それはおそらく年末年始で日常が変わる、具体的にはTV番組がいつもと違ったり、急に家族が来て張り切ったり、いなくなって寂しくなったり、そういう変化にうまくついていけないのだと思います。
これは当たり前のことで、我々元気な人でも年末年始で連休した後、仕事に身が入らなかったり、なんとなく体調が悪いというのはあると思います。
ただご高齢の方にはこの変化、堪えるようなので注意していただきたいです。
ご家族や関係者は高齢の方の変化に注視する時期だと私は思っております。
さて、私の主任ケアマネの研修は無事進んでおります。
12月24日、1月14日に3.4日目の研修がありました。
残りは6日間なのでまだ半分にも来ていません。
今の感想なのですが、私はこの研修を受けてよかったと思うようになりました。
恥ずかしながら失効したせいで2回目の研修なのですが、2回目だからこそ理解が深まるということもあります。
今回せっかく参加しているのだから、毎回何らかの知識を持って帰ろうと貪欲に研修に臨んでいます。たまに疲れて居眠りしたこともありましたが(笑)
12月24日の研修は、医療や多職種協同についての研修でこれについては日頃からやっていて不得意ではないので、なるほど!と聞いている感じでした。
1月14日の研修は「対人援助者監督指導」という内容で、これはあと2日続く主任ケアマネ研修の胆ともいえる大切な部分です。
対人援助者監督指導...こう書かれるととさっぱり意味が分からないです。
人に対して援助をする人が監督や指導をすること、ということでしょうか?
漢字で書くと無駄に難しく感じます。
英語で言うと「スーパービジョン」です。
このスーパービジョンという言い方はケアマネはよく聞くのですが、それが何か?と説明するのはなかなか難しいです。
Supervisionというのはこれで一つの名詞で、監視、管理、監督と訳されます。
スーパーバイズSuperviseというのは動詞で監視する、管理する、監督するということです。
文字通りにしてしまうと、管理者が職員を管理、監督するという上から目線なものになってしまうのですが、実際は教育や指導や助言を通じ成長を図るということです。
ケアマネージャーの仕事は、一人で行動する時間が多いです。(入社してしばらくの仕事がわからない時期は管理者の同行などがあり別ですが)
ケアマネは一人でも仕事に取り組めるように、自発的に仕事・成長をしていくことが必要です。
そのきっかけを与えるのが、スーパービジョンになります。
管理者が厳格に、監視し管理し監督するというのも、組織のクオリティを保つうえで必要ではあるのですが、それだと軍隊のようになってしまい、職場としては息苦しくなってしまいます。
理想的なのは、ケアマネ一人一人が自発的に学ぶすることです。そうすれば結果として組織のクオリティは保たれます。
ではどうしたら自発的にできるかということですが、これは本人が心から必要性を理解しないと自発的にはできないものです。
例えば、サッカー選手がいるとします。
彼(彼女)も練習が必要なことはわかっているんです。
自分から必死に練習する人ならそれでいいです。努力と才能がかみ合えばレギュラーになれるでしょう。
しかし逆に練習が嫌いだとします。
これだと才能がなければ埋もれるし、仮に才能があってもさらに上には才能と努力を併せ持つ人がいます。
後者(練習嫌い)の場合、必要なのがスーパービジョンです。
そのやり方としては、練習嫌いの選手を厳格に監視、管理、監督する、というのも一つの手ではあります。
もう一つのやり方は、自主性を持って練習できるように導くことです。
サッカーだと厳格と自主性の良い例があります。
1998年のフランスW杯の後、日本代表の監督になったのがフランス人のフィリップ・トルシエ監督(写真右側)でした。
当時の日本はまだサッカーはW杯初出場でプロリーグができてまだ5年。サッカー文化は未成熟だった時期に賛否両論はあったもののトルシエ監督のような厳格な監督が必要でした。
トルシエ監督は厳格な指導でユース代表から小野伸二や稲本潤一、高原直泰、遠藤保仁などの黄金世代と呼ばれる世代を導きワールドユース準優勝、その後黄金世代の多くがオリンピックに行きベスト8、そのメンバーを従来の代表選手と融合しアジアカップ制覇、大陸王者の大会のコンフェデレーションズカップをなんと準優勝、最終的には2002年の日韓W杯では初のグループリーグ突破を果たしました。
これはトルシエ監督が、厳格に選手を管理した結果で出た好成績でしたが、反面で選手との軋轢は大きく、当時のエース、中田英寿選手は代表の辞退を考えたほどだったそうです。
トルシエ監督のような厳格なスーパーバイズに対し、自主性を養うスーパーバイズの例があります。
トルシエ監督の次の日本代表監督は選手の自主性を尊重したブラジル人のジーコ監督(写真左側)です。
ジーコは自身が天才的な選手だったためカリスマ性が高いのはもとより、Jリーグの創成期、鹿島アントラーズを常勝チームへと育てた人格者としても知られていました。
トルシエ監督が育てた黄金世代は成熟しつつあり、海外に出ていく選手も増えました。
成熟された選手たちの自主性が尊重されたチームはアジアカップの連覇、2006年ドイツW杯出場など一定の成果を収めますが、勝負の世界は厳しいものでW杯はグループリーグ敗退で終わってしまいました。
ジーコ監督の日本代表は非常に良いメンバーがそろっている強力なチームでしたが、選手の自主性を尊重したところ、逆に具体的な指示がないことを不満に思う選手や、試合の采配にも選手任せすぎて曖昧さが見られたそうです。
厳格か自主性か、スーパーバイズの難しさを物語っている貴重なエピソードだと思います。
どちらが正しいということもないのですが、サッカーの監督においては規律を重んじる厳格な監督が多いようです。
モウリーニョもグアルディオラも、ベンゲルもファーガソンもみんな厳しそうに見えます。
サッカーチームは厳格でよいと思います。
ビッグクラブのバルセロナやマンチェスターCで働くことは名誉だし高給なので、加入や継続を望む選手は世界中にいくらでもいるし選手は規律を守って当然なわけです。守れない選手は出ていくだけです。
しかし福祉業界はそうではありません。
ケアマネのなり手が少なかったり、ケアマネ自体が少ないです。つまりバルセロナとは逆です。
せっかく入ってきた人材に管理者が「言うとおりにしてもらう!」とか「ここでのルールは俺だから!」と厳格に話したら、そんなやばい会社直ぐ辞めてしまうでしょう。
つまり福祉業界は厳格な指導はよろしくないのです。
そこで自主性を引き出すスーパービジョンが求められます。
ただ、よほどの人格者でもない限りそういう指導力はありません。
主任ケアマネ研修にケアマネになってから最短で5年で参加している人もいるので一様に人格者ということはないと思います。
そこで、誰でもできるスーパービジョンの手法をいくつか教わりました。
例えば、
・する人と受ける人は対面して座らず、90度で座る。そうすることで圧迫感がなくなる。
・適度に目を合わせるようにすると説得力が生まれる。
というようなものです。注意すべき点はたくさんあります。
手法ばかりでは浅薄なものになってしまうのですが、大切なことはスーパーバイズには「信頼関係」が必要ということです。
信頼関係のない相手から何言われても教わっても、自主性は引き出されませんよね。
する側、受ける側の信頼関係こそ、スーパービジョンの基本です。
難しいし努力がいるな、と感じた研修4日目でした。
5日目、6日目も引き続きスーパービジョンが学べるので楽しみです!
画像のトルシエ監督とジーコ、懐かしい(20数年前)です。画像も解像度が荒い。
トルシエ監督は昨年アジアカップでベトナム代表を率いていて日本代表との対戦がありました。
スーパーバイズの話でサッカーの監督をしてしまったのですが、サッカーの監督はスーパーバイザーではなく「manager」「head coach」です。
写真のスープのようなものは研修3日目のランチで行った神保町のロシア料理店「サラファン」(千代田区神田小川町3-10-3)のボルシチです。クリスマスイブの寒い日、温かいボルシチは沁みました。ここは6年前の主任ケアマネ研修の時も来たのですが、不思議な感じの店員さんがいい雰囲気を出してます。
4日目は再び「うどん丸香」(千代田区神田小川町3-16-1)の肉うどんです。そんなに多く並んでなかったので、並んでみました。やっぱりこの店のうどんはうまいです。
私は普段ほとんど多摩地域から出ない生活で、今回のように何日も決まって集中的に都会に行くことがないので、研修があるとランチ時は妙にテンションが上がります。
研修の参加者のほとんどは23区のケアマネ(聞くと多摩地域のケアマネはZOOMで受ける人が多いとか)なので都会は珍しくないでしょう。
これだけランチ時を楽しめるのは、逆に多摩からきているお上りケアマネの特権です。笑
文:池端祥一郎
調布 三鷹 狛江 ケアマネ 介護支援専門員 求人